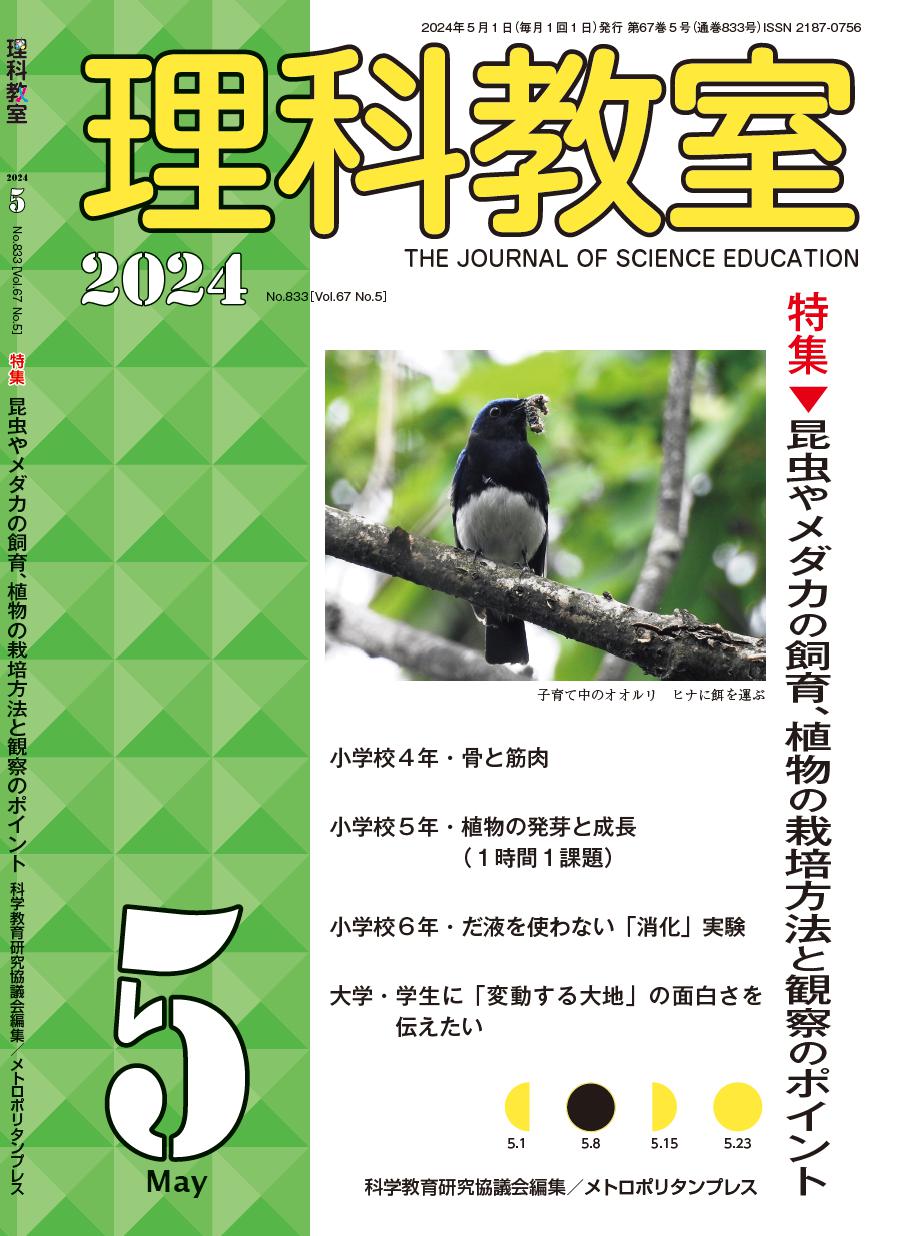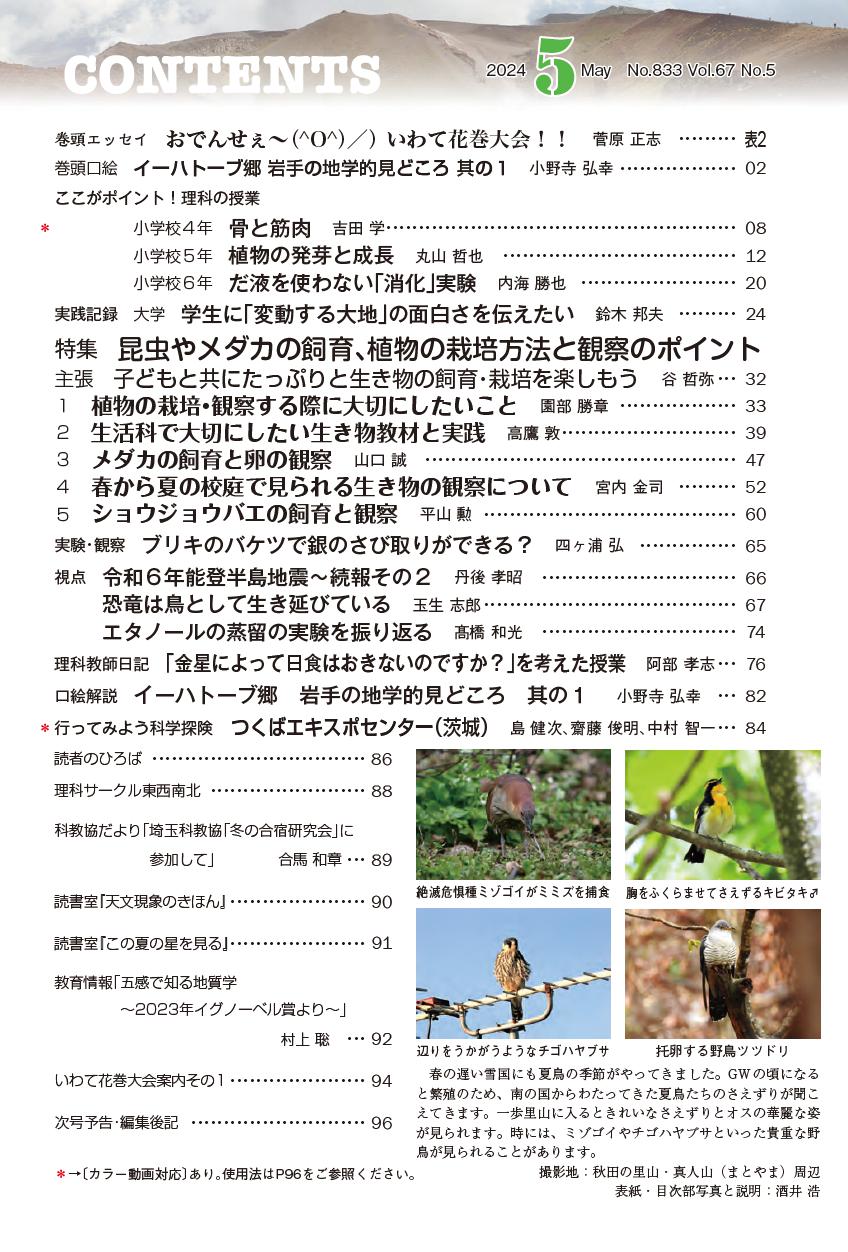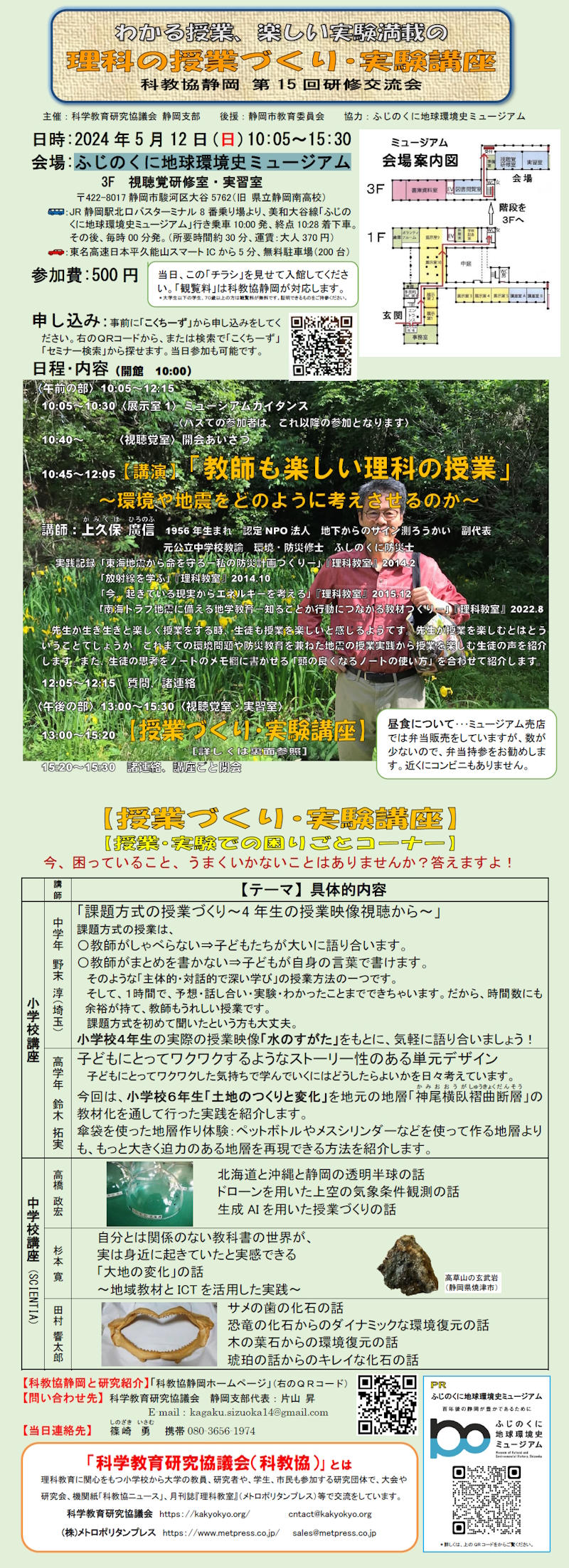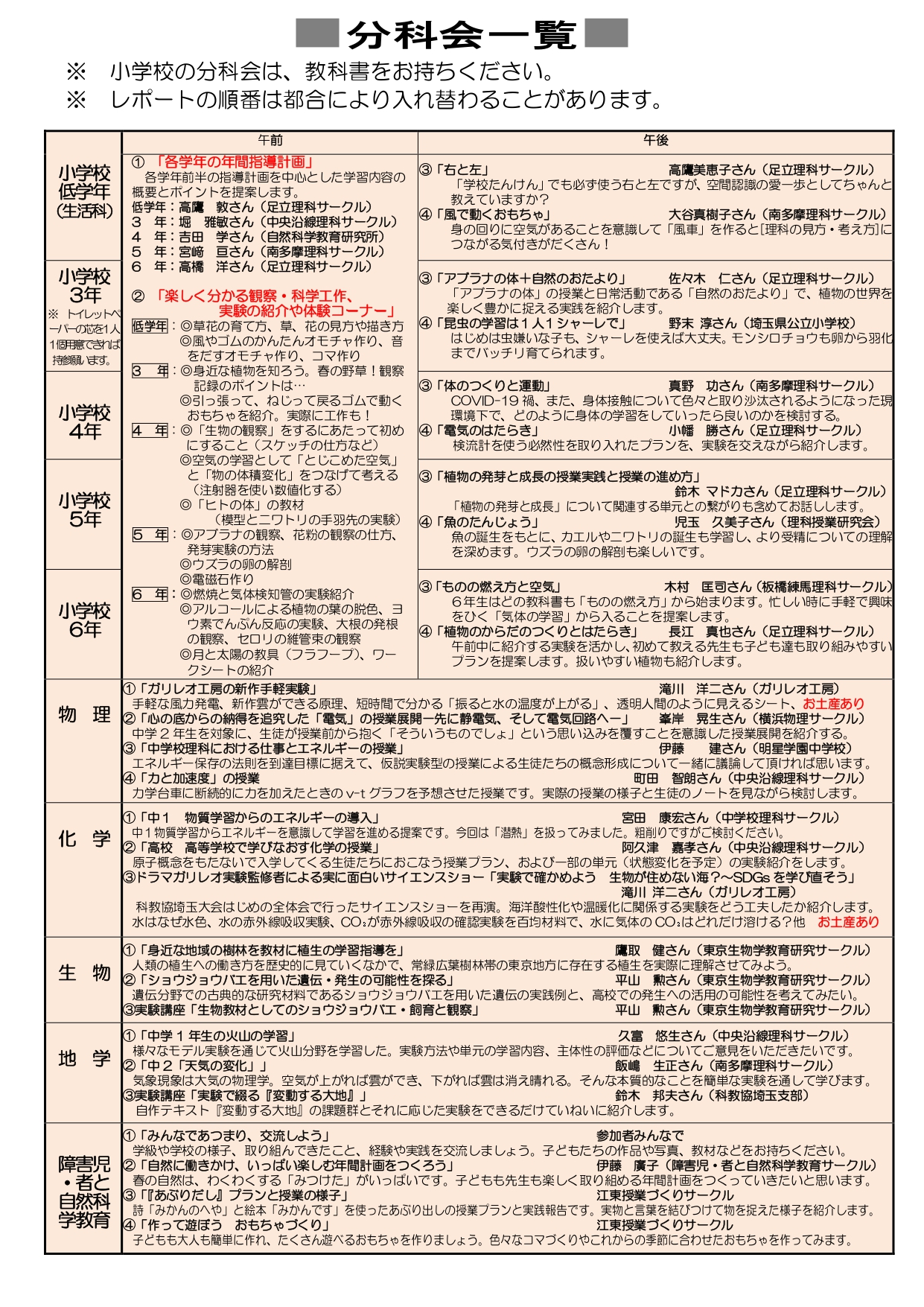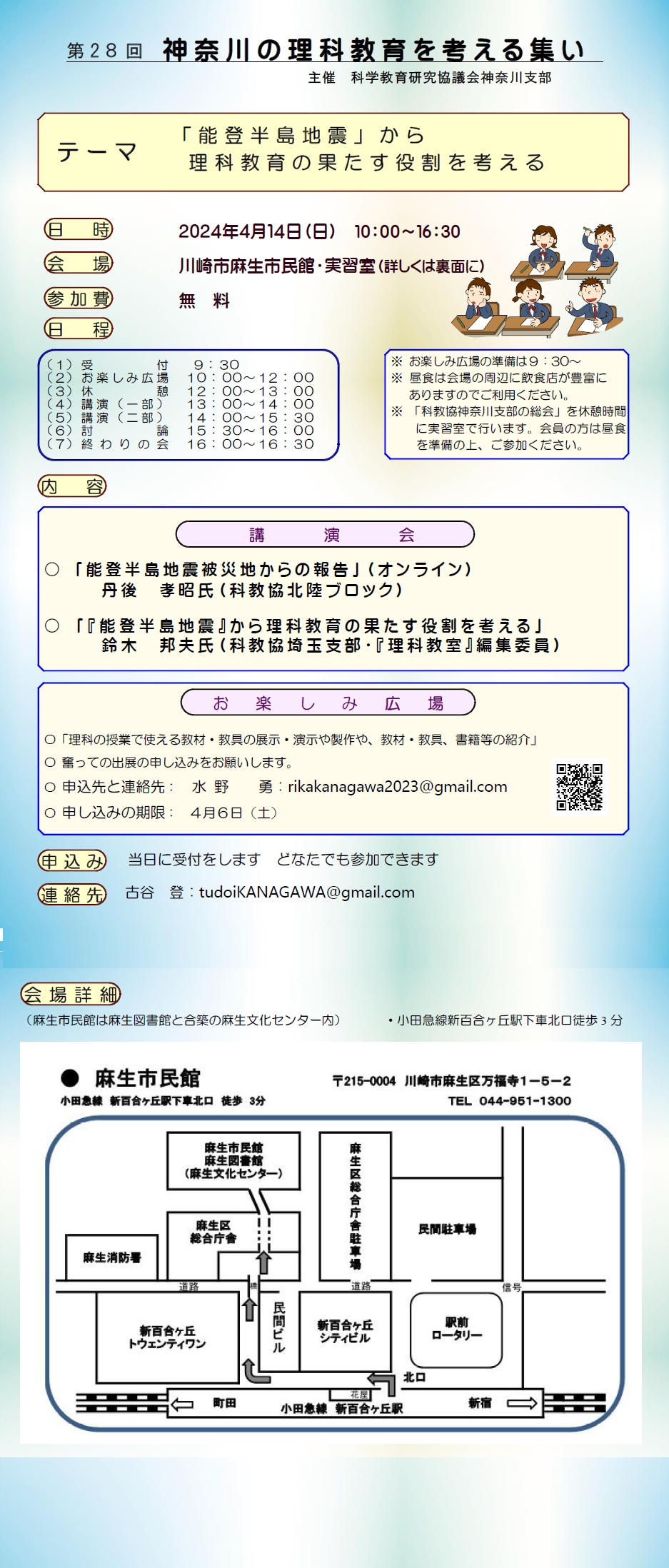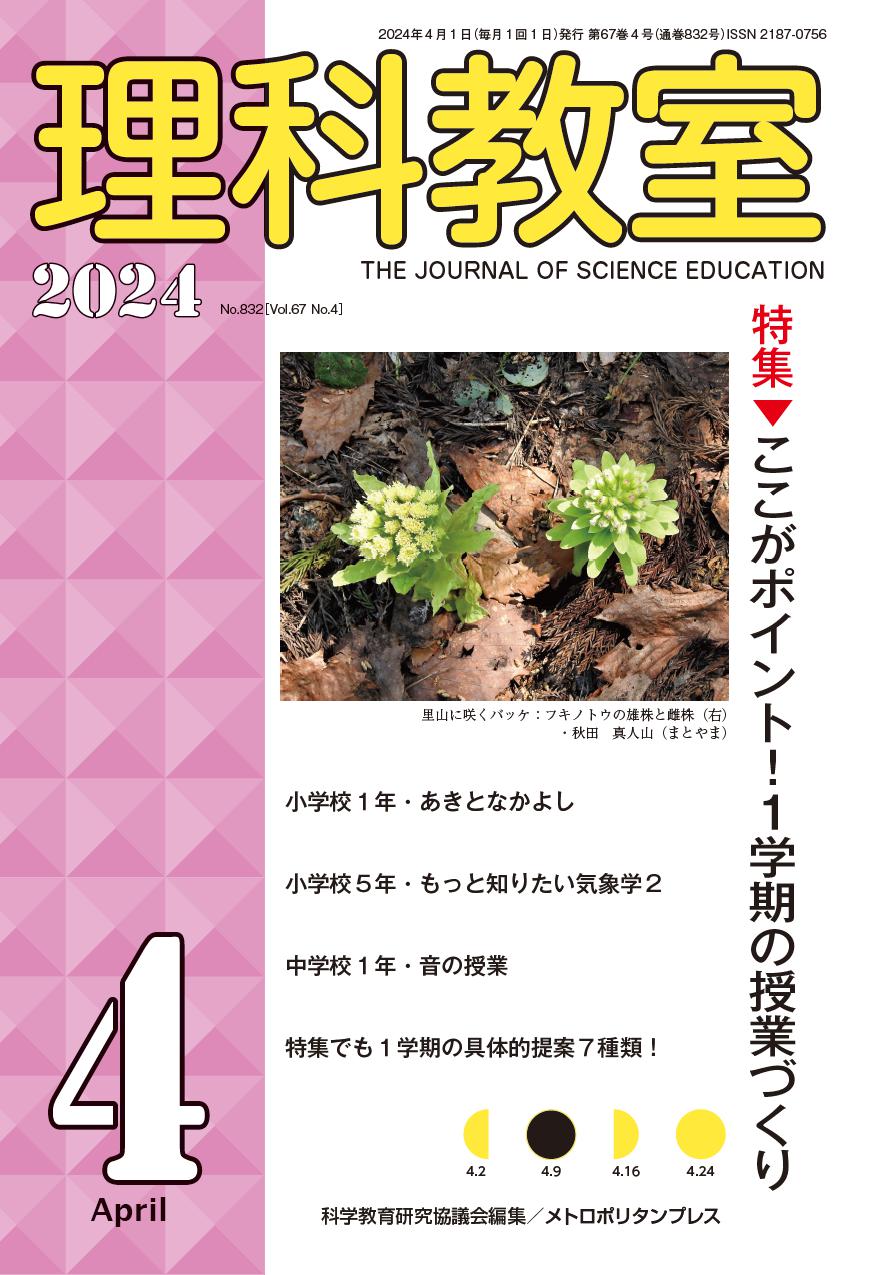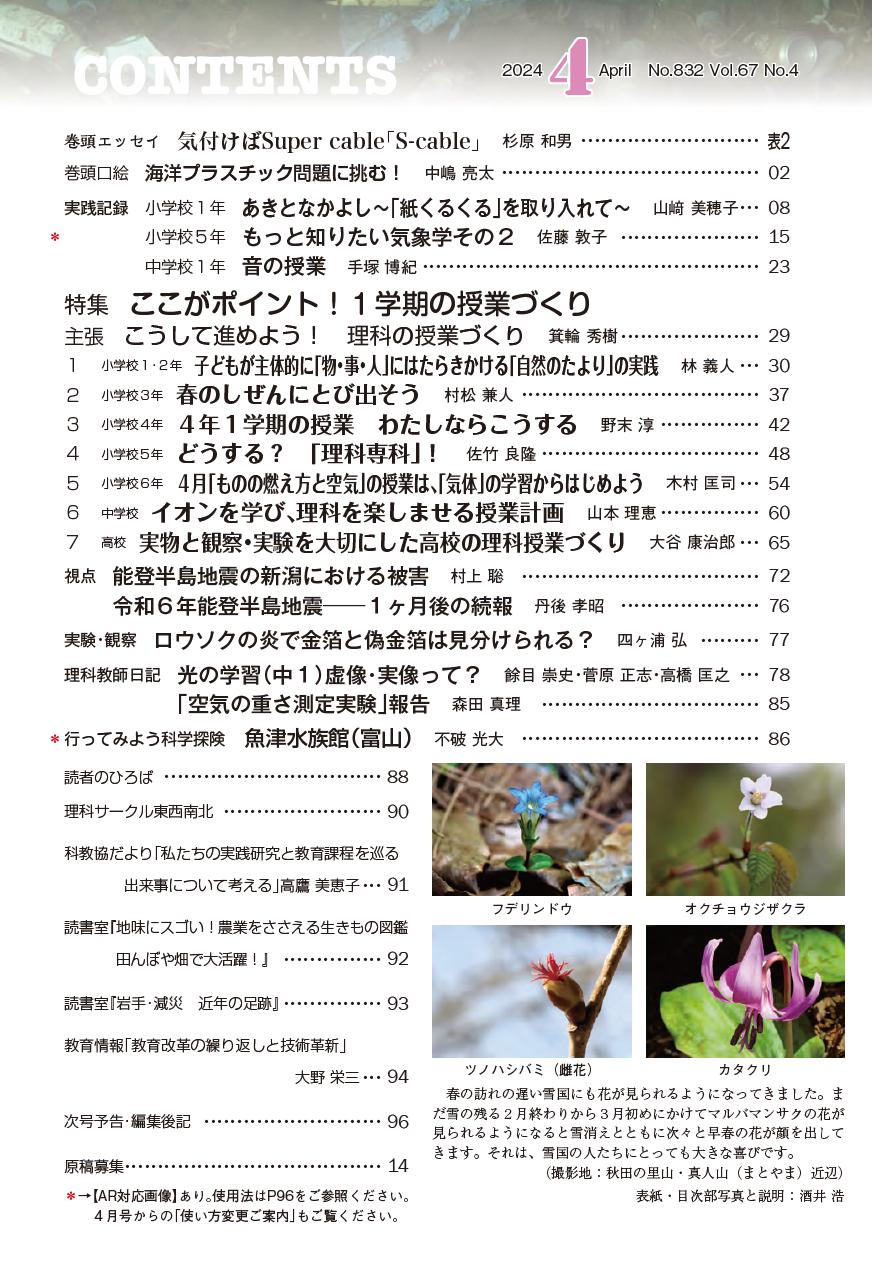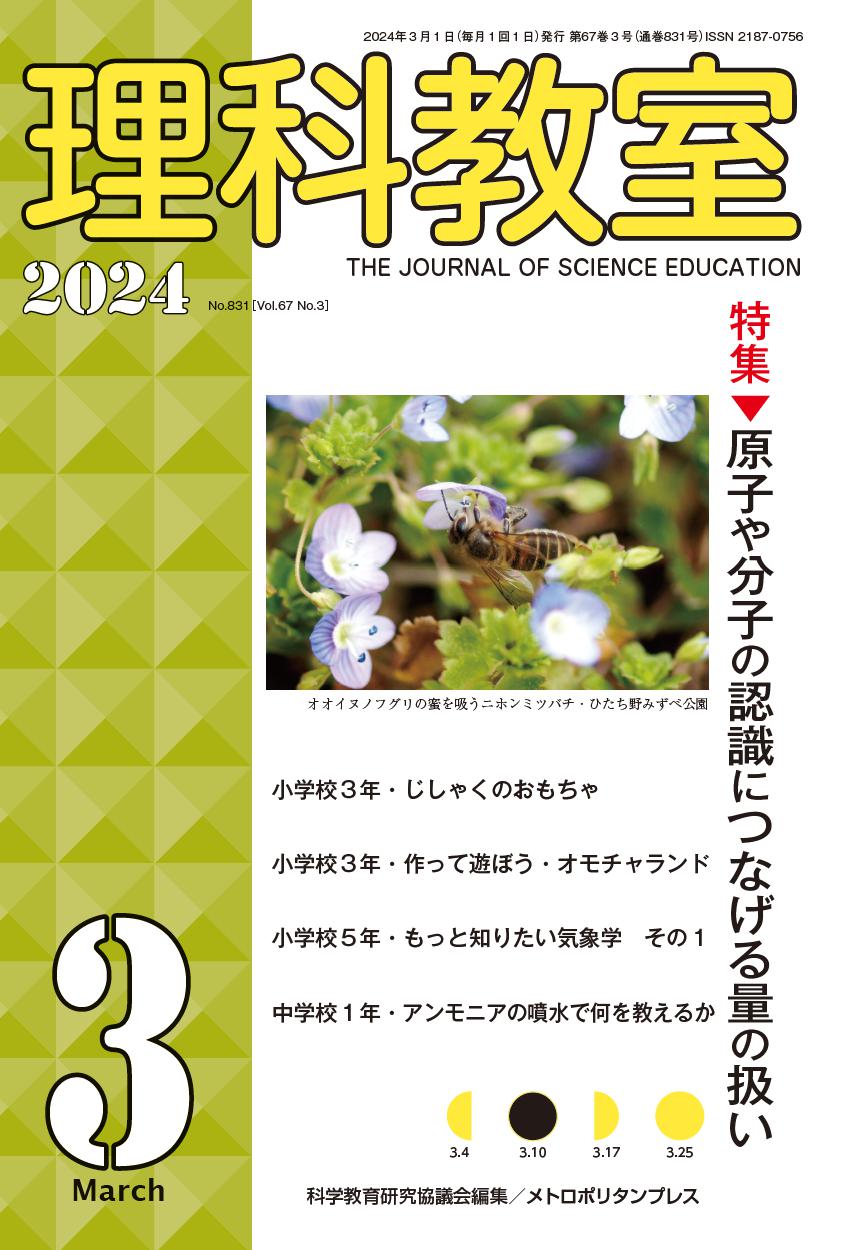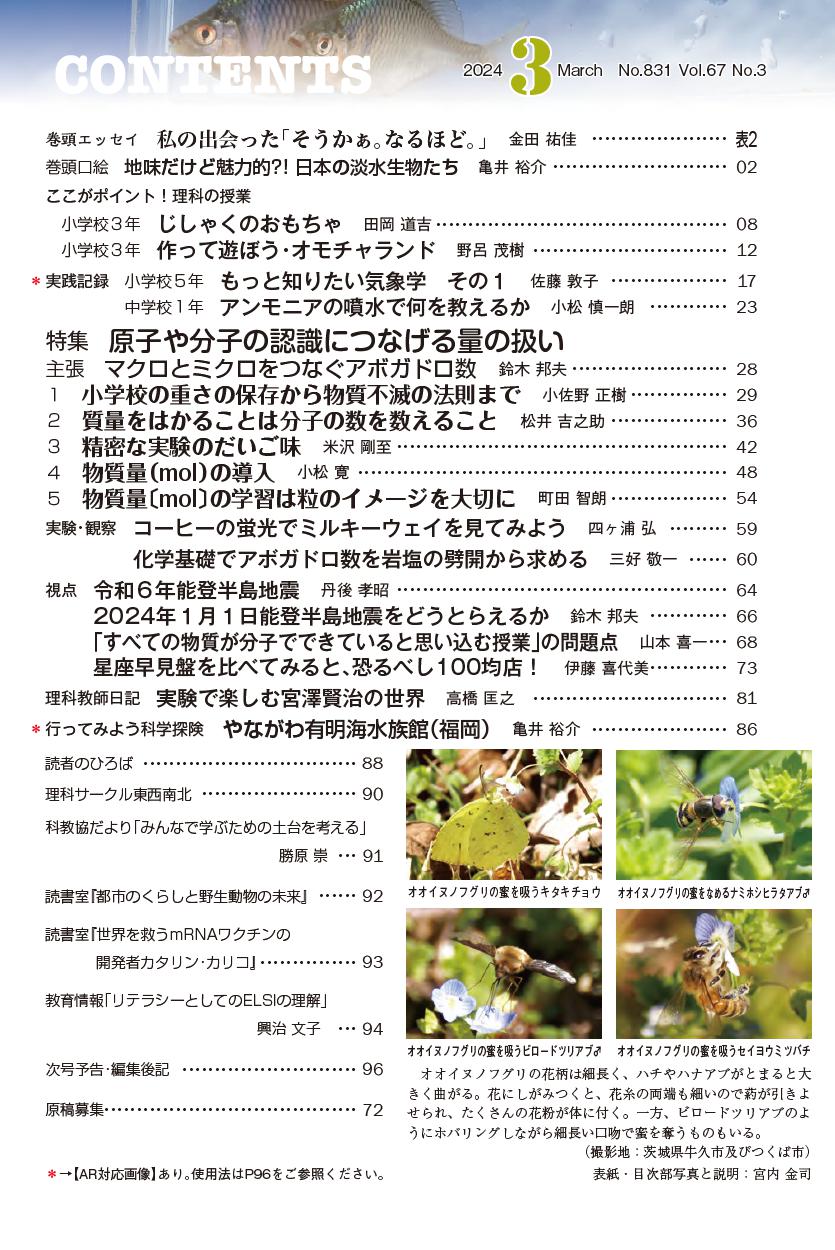Zoomで全国の先生方と交流しましょう。 参加費は無料です。
- 日時:2024年5月18日(土) 10:00~11:50(9:50 ZOOM開始)

- 内容:
- 10:00 アイスブレイクと運営者自己紹介
- 10:05 5年 天気と情報2 佐藤敦子
- 10:40 3・4年 自然観察と生き物 宮内金司
- 11:15 4年 骨と筋肉 吉田 学
- 11:50 終了
- 参加申込方法:
次の「こくちーず」からお申し込みができます。
こくちーずイベントページ
※ 「こくちーず」にメールアドレスを登録してお申し込みください(無料)。 - 申し込み締め切り:5月15日(水)
- ZoomミーティングIDとパスワードの送付:5月16日(木)~17日(金)
参加申し込みをされた方に、ZoomミーティングIDとパスコードをお送りします。
資料は、当日Zoomに参加したときにお送りします。Zoomで受け取れない方にはメールでお送りします。
過去にお申し込みいただいた方には案内メールをお送りしています。
ご不明な点はメールにてお問合せください。
「ここがポイント理科の授業」Web講座担当
箕輪秀樹
月刊誌『理科教室』の定期購読はこちらからお申し込みができます。
https://kakyokyo.org/archives/5669